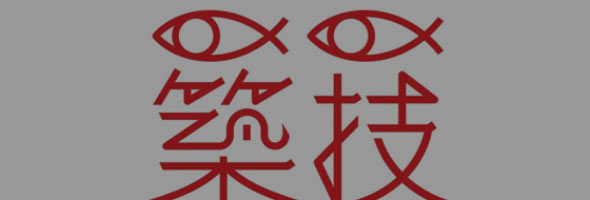築地を知る | 築地昔話館 | 女たちの語り
終戦後、無我夢中で働いて
唐沢よしさん(大正2年生・唐沢商店)

唐沢よしさんは八十一歳。栃木の農家の出身である。 「兄弟は何人いたか正確にはわからない」ほど大勢いたという。 よしさんはその末っ子として生まれたが、十七歳で母を、十八歳で父を亡くした。 さらに年のはなれた兄弟も分家したりで、しだいに農家を継いでいく人がいなくなり、 よしさんは東京に出る決心をした。
東京までは兄に連れていってもらい、兄嫁と本所の三畳一間で幕らすようになった。 タイピストになろうと思ってよしさんは学校に通っていたが、 「タイピストになるといったって容易なことじゃないのよ。 いっそのこと、うちに来なさいよ」と知り合いになった友達に言われた。 その人の母親という人は体が弱くてほとんど寝たきりだったので、 よしさんは住み込みで身のまわりの世話や家事全般をすることになったのである。 その後は本所に戻り、タンス屋に部屋を借りて凸版印刷に勤めた。 「タンス屋のおじさんとおばさんから養女にならないかって言われて、 わたしもそのつもりでいたんだけど、隣の吉岡屋(漬物)さんから縁談があって、 主人といっしょになったわけよ」
夫の虎五郎さんは戦前から吉岡屋に勤めていた人である。 戦時中は夫が東京に残り、よしさんは赤ん坊だった息子の謹志さんを連れて、 一年ほど栃木に疎開した。 終戦後、疎開して留守になっていた吉岡屋の店の方の番をしながら隣に住んでいたが、 同じ並びにいた北村さんという人に「なにか商いをしなければ食べていけない」 ということで吉岡屋の社長に相談したところ、奈良漬を五樽くれた。 つまり、売場と商品を提供してもらい、それを北村さんと二人で売った。
新橋の数寄屋橋の闇市にも、赤ん坊をおぶって出かけていっては食べ物を売った。 「お米を疎開先の栃木からもらってきて、おにぎりをつくったのよ。 そのころは海苔が統制だったから、塩をつけるだけのものなんだけど、 あっという間に売れるのね。 干し芋もずいぶん売ったね。新聞紙を三角に折って三本くらい入れて売るのよね。 それから、素人の人がどこかで手に入れたお酒を買って、 それを飲み屋さんに売りに行くんだけど、一度だけ捕まっちゃったわね」 とよしさんはおかしそうにケラケラと笑う。
十五歳上の夫はもともと体が弱く、そのままサラリーマンでいても、 「もし万が一のことがあったらたいへんだ。商売をはじめよう」 ということで、吉岡屋を退職。 隣が漬物屋ということもあり、同じ漬物で商売するわけにもいかず、 昆布、切りいか、佃煮類を売ることにした。 近所に住む人たちにも助けられながら、よしさんは夢中で働いた。
しかし昭和二十八年、よしさんが四十歳のときに夫は亡くなった。 「つらいとか苦しいなんて思ったこと、ぜんぜんなかったわね。 考えている暇がなかったのね。なんとかしなくちゃ、それだけよ。 あの頃、百万あったら家が建つよといわれてたの。 やっと、百万貯めて大工さんに頼むと、あと五十万貯めなきゃダメだよと言われる。 それでまた、一生懸命働くの。 だから、つらいなんて考えていられない。まして、再婚どころじゃないのよ。 とにかく家だけは自分のものにしなきゃと思って働いたわね」
好景気にわく昭和三十年代、よしさんは念願の家を建て、息子を大学にやった。 無我夢中で働いてきたのである。 だから、息子の学校の父兄参観日などには行ったことはないが、 一度だけ、息子が通う幼稚園に行ったことがあった。 その日のことははっきり覚えている。 「ちょっと、子供たちの様子を兄に行かない?」 と近所の人に声をかけられたよしさんは、 ツギだらけの割烹着を来たまま、大急ぎで幼稚園に駆け込んだ。 すると、音楽の時間に太鼓をたたいているわが子の姿が目に飛び込んできた。 よしさんが学校に行ったのは、後にも先にもそのときだけである。
十年間ほどは、新大橋にある家には帰らないで、店に寝泊まりして頑張った。 店と家の往復の時間を惜しんでのことだった。 冬でも夏でも土間に箱を並べ、その上に座ぶとんを敷いて寝た。 「なにがなんだか、わからないうちに年月が経ってしまったという感じよ」 というよしさん、当時を振り返ってみても苦労の二文字は浮かばない。
八十一歳の現在もよしさんは店に出ている。 なんと、午前一時半(!)には店に人り、閉店まで働く。 小柄で華奮な体からは想像できないほど元気だ。 「昔はこんなに細くなかったわよ。十五貫くらいあってね、 お産以外では医者なんてかかったことがないのよ。 この前、初めて病院にかかったわよ。 話をしている分にはみんなに元気だって言われるけど、 これでけっこう腰とか、腕が痛くなったりするのよ」 現在は謹志さん一家といっしょに暮らしている。
楽しみはなんだろうか? 「こうして店に出て、みんなとおしゃべりするのが楽しみね。 店に出ているとみんな忘れてしまうものね。 わたしは、うちに帰ったらなんにもしないの。 このままゴロって横になっているの」 とよしさんは屈託なく笑った。
(平成6年 龍田恵子著)