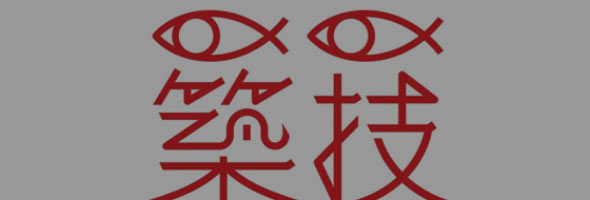築地を知る | 築地昔話館 | 女たちの語り
床店からはじめて、七十年
小見山よしさん(明治40年生・小見山商店)

日本橋の魚河岸が関東大震災によって移転を余儀なくされ、一時、芝浦にいて、築地 へと移ってきたことは、周知のとおり。小見山商店は、その魚河岸の移転と共に芝浦を経て、築地は市場通り(新大橋通り) に床店を出した。大正、十二年十二月のことである。そこはもともと墓場で、その上に立っていた塀が震災で崩れ、土台だけになってしま った。当時、この周辺は佃政の親分という人が仕切っていたことから、石を全部取り除いて 床店をつくってくれたという。小兄山よしさんは八十七歳。 現在、店の方には出ていないが、当時からの築地を知る数少ない一人である。長男の順一郎さん夫帰と同居する下総中山のお宅に訪ねた。
「間口、奥行き三尺の床店を二軒貸してもらって商売したのよ。床店は全部うまった わね。そのときの店でいまも場外に残っているのは、鰹節の秋山さんと牛丼の大森 さんくらいなものね」 とよしさんは言う。 板橋の家からその床店に通っていたのだが、生活の場もいっしょにした方が便利だと いうことから、二年後に現在地に移った。 そのころの住まいは、震災で家を焼かれた人たちが新しく立て直したものがほとんど で、普通の民家と同じスタイルだったが、それを借りた。 家賃は当時の金で四十五円。魚河岸が東京卸売市場としての業務を開始した十年ころ までには客も場外の方に流れ、少しずつ活気が出てくるようになり、店の数もふえて いったという。
よしさんは本所で生まれた江戸っ子である。家は“一大身上の一大貧乏”といわれた 株屋だった。儲けるときは大きいが、損をするときも大きい。 「わたしが三つのときに母親が死んだのよ。 そのころは景気がよかった。家も大きくてね。 ところが父親はそれをあくる日には売っちゃって、すっからかんになってしまった んです。でも、わたしが十三歳のころにまた芽を吹いて、おひな様を買ってもらっ たり、ちりめんの着物をこしらえてもらったりしました。 父親は子供をおじいさん、おばあさんに預けっぱなしでね。 そのあとすぐに父親は亡くなったのよ」 そんな浮き沈みを目の当たりにしてきたからか、「人生さばさばしたものよ」といっ た気っ風のよさがある。
よしさんは十六歳で結婚した。 結婚といっても格別にあらたまったというものではなく、たまたま近所にいたから自 然にいっしょに暮らしはじめたといった感じだったという。 だから、いまのような結婚式はあげていない。しかし、現代のように多額の費用をか けてする結婚式に比べると、なんとシンプルで合理的であったことか。 震災の年に、四畳半と三畳の家を借りて新婚生活がスタートした。 家賃は十二円だった。夫の一郎さんは三越で働いていたが、二十歳のときに河岸に出 て、荷車を引いて経木を売って歩いた。それがいまの商売のはじまりである。 それにしても十六歳で結婚してそのまま商売の道を歩むことになるのだが、不安はな かったのだろうか。 「不安なんてなかったわよ。食べていかれりゃいいって感じよね。 昔はそんなもんだったですよ。働かなければ笑われるもの。 おかみさんというのは、子供をほっといても働け!という時代だったのよ。 明治生まれの男は、やっぱり男の方が上位にあるっていう考え方ですからね」
商売の方は順調に伸び、特に落ち込んだこともなく、経済的に苦労をしたという経験はない。 しかし、夫の分まで働いた。 というのも、当時、店の主人は昼ころになると遊びに出かけてしまい、必然的におか みさんが働くようになる。帳場に座るのはだいたいおかみさんで、金銭を握っていた。 よしさんも例外ではなかった。店が忙しいから、食事の支度もできなかった。 子供が学校に持っていく弁当は「うちの子供はあたたかい御飯でないと食べなかったから」 ということで、店の人が学校まで届けていたという。 「夫は朝店に出て、そのあと出ていくの。たまに小唄の稽古に行く、なんて出ていく んだけど、どこに行ってるものなのか、わかりません。 帰ってきても、どこに行ってたなんて言いやしませんよ。 どこに行ってたのって聞くと、また出て行ってしまうんですからね。 泊まってくるということはなかったけど、帰りはいつも十二時すぎ。 わたしは朝が早いので起きていられません。 それで済んでいた時代だったのよね」 そう言ってよしさんは笑うのである。 それでも夫の行き先は気になって 「一体、いつもどこに行くのだろうか。今日こそシッポを捕まえるわよ」 と電話ボックスの中に隠れて、夫が行く方向を目で追った。 息子を連れて家出したこともある。 その一方で「亭主の恥は女房の恥」ではいけないというので、夫の紙入れをのぞいて 中身が少なくなっていたら、そっと札を入れておくという気配りもみせた。 それでは耐えるのは女だけ?とは早計すぎる。夫帰で外出することも多かった。 「小見山さんのところは夫婦そろって外出できていいねえ」と人もうらやむ関係(?) でもあったのだ。 また、喧嘩らしい喧嘩もしたことはなかった。 「だいたい夫が取り合ってくれないのよ。太刀打ちできないのね。 でもね、よく二人で外に食べに行きましたよ。 ふだん、食事は女中さんまかせだったけれど、たまに家族そろって銀座で食事した り、店の者を連れて浅草に行ったりしたわね」 ひとつ屋根の下に住んでいながら、商売が忙しく家族が顔を合わせて食事もできない 時代だったが、だからこそ、みんなで出かける喜びはひとしおだったに違いない。
長男の順一郎さんがこう言った。 「おふくろというのはいつも怒鳴って、ものさしを持って子供を追っかけまわすとい うことしか覚えてない。ところが、親父は遅く帰ってきても必ずおみやげを買って きてくれるから、うれしくなったもんですよ。 戦後、男は女をいたわらなければならないという風潮になったけど、それは昔もそうだった。 ただ、表現のあり方が違っていたのでしょうね。 男というのは家庭の基礎をしっかり持たなくてはいけない。 暮らしを優先させなくてはいけないという義務感がいま以上に強かった。 その上に立って、男はなにをしてもいいという考え方があったのでしょう。 それと昔は、店と家庭が交錯していたから、男は外に逃れるしかなかったけど、 女の方はそうもできない。 でも、案外女性たちは店と家庭を自分なりのイメージで分離させていたのかもしれ ないですね」 よしさんは「苦労という苦労はしていないわね。しいていうなら、夫で苦労したかな」 と笑った。 その時代、男には「おれについてこい!」「おれにまかせろ!」という気概があった。 たくましい夫についていくのは、女冥利に尽きること。 だから、苦労のしがいもあったのだろう。
(平成6年 龍田恵子著)